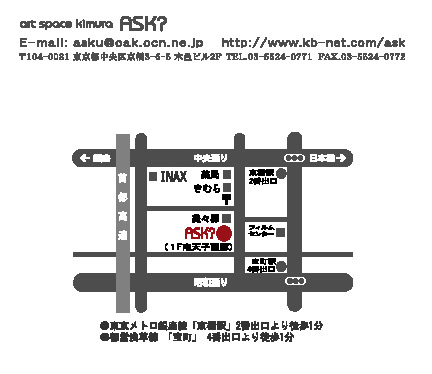初冬の暖かい日には、ふと、子供の頃、母がよく蒲団を作っていたことを思い出す。 その頃の庶民の家庭には、まだ羽蒲団などというものはなく、冬の蒲団と言えば、「木棉わた」が当り前だった。 古いわたを蒲団屋に頼んで打ち直し、それが薄く積まれて戻ってくると、母は決まって近所のおばあさんに来てもらうのだった。
朝から二人は縁側に座って、世間話をしながら蒲団の側(かわ)を縫う。 表には、大抵、母の古い着物が使われて、違った柄があちこち縫い合わせてあった。 「わた埃を吸うから、あっち行ってらっしゃい。」と言われながら、私は縁側の隅に座って、二人の話を聞いていた。 おばあさんが、お嫁さんに遠慮しいしい暮らしている話をしたり、母が、引揚げの時死んだ、姉の話をしたり、、、そのうちに、いつの間にか蒲団の側は縫い上がるのだった。
夕方、それを座敷に広げて、薄いわたを、慎重に、均等に、広げてゆく。 すると座敷は、雲が降りてきたような、非日常的空間に変わるのだった。 そして二人は、縁だけに、更に、わたを重ねて厚くすると、四隅を持って、掛け声と共にひっくり返す。 すると手品のように蒲団が出現する。 大きく膨らんだ、出来立ての蒲団を、わたが動かないように長い蒲団針で綴じてゆく。
朝から夕方まで一日がかりで仕上げる、その行程は、大人たちにはせわしいものであったろうが、子供の私には、時間がゆっくり流れていた証しとして、忘れることができない。 今では家庭で蒲団を作ることもないし、蒲団自体も、重いものより軽いものが好まれる。しかし、あの座敷の光景が甦るせいか、私は、重くて暖かい冬蒲団に潜りこみたくなることがある。
-
最近の投稿
カテゴリー
最近のコメント
- 「個展のお知らせ」 に naoeve より
- 「個展のお知らせ」 に ジョヴァンニ・スキアリ(佐藤史土) より
- 「展覧会のお知らせ」と「ブログ終了のご挨拶」 に nao より
- 「展覧会のお知らせ」と「ブログ終了のご挨拶」 に ruri より
- 「屋上の風景」 に nao より
カウンター
81,230アーカイブ
- 2025年12月
- 2025年8月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年10月
- 2024年8月
- 2024年3月
- 2024年1月
- 2023年6月
- 2023年3月
- 2023年1月
- 2022年4月
- 2022年1月
- 2021年11月
- 2021年6月
- 2021年2月
- 2019年12月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2017年9月
- 2017年1月
- 2016年9月
- 2015年3月
- 2014年12月
- 2014年9月
- 2013年10月
- 2013年3月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年6月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2011年1月
- 2010年12月
- 2010年10月
- 2010年9月
- 2010年8月
- 2010年7月
- 2010年6月
- 2010年5月
- 2010年4月
- 2010年3月
- 2010年2月
- 2010年1月
- 2009年12月
- 2009年11月
- 2009年10月
- 2009年9月
- 2009年8月
- 2009年7月
- 2009年6月
- 2009年5月
- 2009年4月
- 2009年3月
- 2009年2月
- 2009年1月
- 2008年12月
- 2008年11月
- 2008年10月
- 2008年9月
- 2008年8月
- 2008年7月
- 2008年6月
- 2008年5月
- 2008年4月
- 2008年3月
- 2008年2月
- 2008年1月
- 2007年12月
- 2007年11月
- 2007年10月
- 2007年9月
- 2007年8月
- 2007年7月
- 2007年6月
- 2007年5月
- 2007年4月
- 2007年3月
- 2007年2月
- 2007年1月
- 2006年12月
- 2006年11月
- 2006年10月
- 2006年9月
- 2006年8月
- 2006年7月
- 2006年6月
- 2006年5月
- 2006年4月
- 2006年3月
- 2006年2月
- 2006年1月
- 2005年11月
- 2005年9月
- 2005年7月
- 2005年5月
- 2005年4月
- 2005年2月