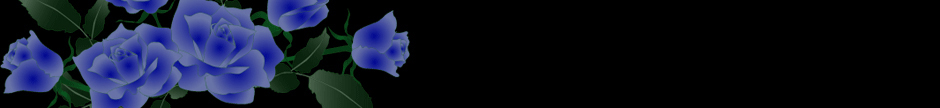ロクデナシ
その頃『世界に一つだけの花』という曲が流行した。
〝№1にならなくてもいい
もともと特別な ONRY ONE〟
それはそれでいいだろう。それはそれでそう思えれば幸せだろう。
でも僕は№1になりたかった。安隠とした平単な毎日に自分を置きたくなかった。
「この中で全国模試三位の人間がいる。――溝口泉くんです。」
あたりまえといえば、あたりまえの結果だった。僕は凡人とは違う。かといって天才でもない。でもより完璧に近い人間になろうとする努力をおこたっているわけではない
――№1にならなきゃ、意味がない――
僕をいつもそうかりたてるものは、人々の賞讃の言葉と羨望の眼差しと母の言葉だった。
「泉、なんでもいいから良いことで一番になってちょうだい。泉は何でも良くできるしとってもいい子だもの。母さん期待してるわ・・・。」
下校途中の車内の中で、何度も聞かされた言葉だった。僕は幼な心に、
「母さん!僕が一番になったら誉めてくれる?」
と満面の笑顔で尋ねたことがある。すると母は、誉めてあげるとは言わずに
「泉が世間で有名になったら、みんなをビックリさせて、父さんの借金を全額返済してあげてね・・・。」
と、僕の方を見ずに言った。
僕の父は、長所として人あたりが良かったが、それが短所となり、よく人に騙された。
某人の級友というだけでその保証人になったり、マルチ商法に騙されたりして、ついには自営業の会社を倒産させ、田畑を全部売り払っても、まだ三千万残る借金をしたのだった。
その時から母さんの口ぐせは
「父さんのようなロクデナシになってはダメ!!あんたは父さんとは違う!今に世間をあっと言わす大物になるのよ・・・!!」
と言うのが常であった。
――母さんを嬉ばせたい。誉められたい。父の苦労から解放させてあげたい。その為なら僕はなんだってしただろう・・・。
その思いが今の僕を造った。僕はいつの頃からか自分の価値というものが、人に認められること、母さんに誉められること、その賞讃の言葉全てが僕の存在理由となった。
十六歳の少年が、王者の夢を抱くことはたやすかった。
クラス替えで、鶴町と出会った。僕が初めて興味を持った人間だった。学力が優れているわけでもなく、かといって容姿がいいわけでもない。どちらかといえば、落ちこぼれという部類の人間に入るが、彼はひょうきんで
〝一番、尊くえらいのは自分だ!〟
なんて笑いながら大声で言うものだから、僕はそのバカバカしさに笑いが止まらなかった。
彼の人間的羨望の眼差しを自分に向けたい。本当にえらいのが誰なのか、はっきりさせてやろうじゃないかという気さえおこってくる。
ある日僕は鶴町に冗談で
「お前、自分のこと一番エライなんて言ってるけど、そのエライお前が尊敬している人って誰なんだよ。」
と聞くと鶴町は
「きまってるじゃん。両親だよ。」
と、笑って即答した。その答えは、僕をイライラさせるのに十分だった。
その日、家に帰ると母が泣いていた。パートで働いた金を父がパチンコに使ってしまったらしい。母さんは泣いて僕にすがってきた。
「泉、父さんに何とか言ってあげて!!母さんの生活の為にこんなに頑張っているのに、父さん分かってくれないの!」
女の細腕に、こんな力がどこからくるのかという勢いで僕に抱きつく母。もう三年も前に買ったほころびた服で、散髪も行っていないのび放題の白髪。〝こんな母に誰がした!!〟僕は、自分の力のなさを恨み、父への怒りをあらわにした。
「父さんは、何処にいるの?」
「自分の部屋でお酒を飲んでいるわ。」
「そう・・・。」
僕は父さんの部屋の襖を思いっきり開けた。
「父さん、なぜ父さんは母さんの気持ちがわからないんだ!何に考えてるんだよ!自分のやってることわかってんのかよ!母さんがどんな思いで暮らしてるか知ってんのか!」
と言うと、父は背を向けたまま
「お前、父さんの事どう思う・・・。」
と聞いた。
「最低だよ・・・いっそ死んでくれたらって思うよ・・・!!」
「そうか・・・。」
父は、こっちを見ずにポツリと言った。
それからというもの僕は暗澹とした毎日が続いた。家に帰れば必ずといっていいほど、母が泣いて僕に父の愚痴をいいつけてくる。
正直、勉強どころではなかった。そんな中僕の胸の中には一つの疑問がでてきた。
――父さんの悪口を言う母さん。父さんを愛して結婚したんじゃなかったの?僕は、本当に祝福されて生まれてきたんだろうか?
僕には、両親の愛が信じられなくなっていた。
「――くん、 溝口くん、もう聞こえないの?」
「え、何だったっけ?南」
「あのね・・・。」
南というのは、幼なじみで今は僕の彼女だった。陽気で優しくて穏やかでかわいい。
僕が心を許せる唯一の女。ずっと一緒だった分、何でも話せた。だから僕は南の言葉なら信じられる。ところが、僕は次の瞬間、意外な言葉を聞く。
「あのね・・・。鶴町くんっていい人ね。」
僕はその時、きっと怖い顔をしていたと思う。
いつも楽しそうで劣等感なんて全ったくない鶴町を、そして何よりも、自分が一番尊敬できるのは両親だと笑って答えた鶴町を、南は、僕の目の前で誉めた。僕に何が足りない。
完璧になろうとしている努力をすればするほど、僕は鶴町に全てを奪われてゆくような気がしていた。
その日を境に僕は、精神安定剤を常用するようになった。一時的な心の平安の中でも、鶴町の存在は僕を恐怖させた。
――この薬を飲めば、鶴町のようになれる・・・そんなおかしな妄想まで抱くようになっていた。誰も信じられなかった。もちろん自分すら。
いつのまにか僕は、自分に足りないものを補うかのように薬を服用していった。
学校へ行けなくなったのは、薬を服用してからそう長くはなかった。行きたくても行けないのだ。鶴町の横で南が笑っているようで恐かったのだ。そしてしの笑みが、学校へ行けない僕への嘲笑であるかのような気さえしてくる。いや、南だけではない。世間が世界が、僕の事を嘲笑っているようで、ただ怖かった・・・。
部屋を暗くして、できるだけ動かないようにした。
――太陽に見つかってしまう・・・
僕は陽のあたる全てのものから隠れなければいけなかった。
「泉、あなたどうしたのよ。あなただけが母さん頼りなのよ・・・。」
学校にも行かず、勉強もできなくなった僕に母は、参考書を持ってきた。僕はうつろな目でそれを見て小さく
「母さん、もう本はいらないんだ・・・。友だちが欲しいんだ・・・。」
とだけ言った。
「僕は孤独だった。勉強が出来ない自分に価値をみいだすことなどできなかった。世間から、社会から適応できない自分がはがゆかったが、薬はそんな僕の意識をゆっくりと飲みこんでいった。焦燥感と不安と、僕ではない自分への安定感との空回りの日々が続いていった。
それでもやっぱり薬は一時的なものにすぎなかった。薬が切れると、僕は錯乱した。学校へ行けない自分を責めた。大声でわめいて窓にむかって椅子を投げつけた。そうなると母が決まって
「泉、いい子だから薬を飲んで。お願い。」
と泣きながら、薬を持ってくる。この時の母の涙は、僕への失望感の涙だったのか、愛の涙だったのかはわからない。だってその時僕は自分の事で精一杯だったから。
――今夜死のう。そう決心した。薬でふらつく足で台所へ向かう。収納ドアから包丁を取り出し手首にあてた。ヒヤッとした冷気が僕を興奮させた。思いきって強く押しあてて引いた時、鋭い痛みが体中にはしった。僕は僕の痛みに驚いた。
――まだ痛みを感じるのか!こんなに絶望しているのに。まだ未練があるのか!こんな頭をひきずって生きていかなければならない自分。人としての価値を失っているのに!この痛みが皮肉にも僕に生きていると告げてくる。役立たずのこの僕は真夜中の台所で大声で泣いた。
初めて産声をあげたように泣いた。
〝ここにいる。助けて!愛して!〟
というふうに。
手首を刻んだ夜なによりも、僕の心が痛がっていた。
気がついた時、一番始めに見えたものは白い天井だった。
左手がドクドク痛んで目をやると包帯が巻いてあった。石腹が重いのでそっと頭をあげると、父さんがうつむいて眠っていた。病院だった。父さんが運んだらしい。
僕は起き上がろうとしたが体だがだるくて動けなかった。
「安定剤が効いている。あんまり動かない方がいい。」
眠っていると思っていた父が、うつむいたまま低い声で言った。
「お前どうして自殺しようとした?」
という父の問いに答える気力もなかった。
〝僕にはもう人間的価値がないんだよ〟とは言えず逆に
「父さんは、なぜ母さんと結婚したの?」
と、とりとめのないことを聞いた。
父はうつむいたまま語りだした。
「母さんは、働き者で、何でもできて負けん気が強くて美しい女性だった。俺が結婚の日を選んだ時も、〝その日は社内旅行でハワイに行く日だから〟なんて俺を困らせたりしたもんだ。お前が生まれる前、父さんは浮気した事があるんだ。寝言で〝愛子ちゃん〟と母さん以外の女の名を呼んだ時、母さん実家に帰っちゃって、俺は帰ってきて下さい。お願いします!なんて土下座したこともある。今思えば本当に惚れてたんだろう。
お前が母さんのお腹の中にいる時、旅行したことがある。そこのなだらかな平野で、母さんと約束したのは、二十年後三人でまたこの地にこようと言ったんだ。それなのに、俺は母さんに苦労ばかりさせてしまった。俺には母さんやお前のような才能はない。もっていたものといえば小さな会社だけだ。今はもうそれすらもない・・・。それでも、信じてはくれないだろうけど、父さんの守りたいものは今も昔も、お前と母さんだけなんだ・・・それなのに・・・お前は・・・。私はただ、お前と母さんの笑っている顔を見たかっただけなのに!!」
父はまるでこの十六年間を後悔するかのようにうつむいたまま嗚咽を漏らした。
――この人は不器用なのだ。そして寂しかったのだ。働いても働いても、家族に認められない辛さ。一番幸せにしたい人に罵られる辛さ。僕は何故わかってあげられなかったんだろう。社会的にかけている物が、人間的に欠けているものと、どうして言える?
僕が本当に憎んでいたのは、そんなに何でもできて何でも知っているくせに父の愛を信じられない自分の孤独をおしつけてきた、かわいそうな母へだったのかもしれない。
誰も誉められたい。誰も認められたい。そして誰も愛されたい。ロクデナシは父さんじゃない。父と母の痛みを裁き続けた僕自身だったのだ・・・。
「父さん、僕に言ったさっきの言葉、母さんにも言ってあげなよ・・・。」
僕はそう言うのがやっとで、すぐ眠ってしまった。もう怖い夢は見ないような気がした。
目覚めたのは次の日の夕方だった。ゆっくりと体を起こして窓の外をなんとなく見ていた。コンコンとノックする音がして、僕はドアをふり向いた。
「入るぜ。」
――鶴町だった。
おそらく南が僕の自殺未遂の事を彼に告げたのだろう・・・。もうそんなことはどうでもよかった。僕の心は自然と穏やかだった。友達がきてくれたことの方がむしろ嬉しかった。
「お前、ちょっと見ない間にえらく儚くなっちまったなぁ。」
と、いうのが鶴町の第一声だった。
「相変わらず、君はおもしろいなぁ。」
と、小さく笑うと鶴町は少し驚いたように、
「お前、そんな風に笑えるんだなぁ。」
と、まじまじと僕を見返した。あんまりみてくるものだから僕は恥ずかしくなってしまった。
「いや、なんか昔は、〝俺に触ったらケガするぜ〟って感じで正直怖かった。なんか昔の俺もそんな感じだったから・・・。」
僕は、鶴町のその口調の重たさに同じ匂いを感じた。
――彼にだけ今までの事を聞いてもらおう・・・。そんなことで悩んでいたのかと笑われてもいい。
僕は、今の僕の心の証人をつくりたかった。
僕は鶴町に全部話した。№1であり続けたかった葛藤、鶴町という存在の恐怖、両親の不和、南への不信、両親への疑心、追いつめられる毎日のこと、自殺、父との和解・・・。ゆっくり話すつもりが吐き出すように話していた。安静剤も効果を失うほど、僕は興奮していた。
みんな言いたかった。みんな聞いて欲しかった。僕ごと全部、鶴町だけに受け止めて欲しかったのかもしれない。何がそうさせるのかはしらないが、僕は全部話し終わると泣いてしまった。
「情けないだろう僕は・・・。自分でも自分がこんなに弱い人間だったなんてって思うよ。いつもみたいに笑い飛ばしてくれよ。」
僕は鶴町の顔を見るのが恐かった。ただ恐かった。僕はずっとうつむいたまま涙を流していた。
「お前、今歩けるか?」
僕に背を向けた鶴町に僕は
「ああ。」
と答えた。
「今、夕焼け綺麗だから、屋上あがらないかそう言う話だったら、屋上で聞いてやる。俺こうみえてもロマンチストだから。」
その言葉に僕はパジャマの上からフリースのジャケットを羽織ってベットからでようとしたのだが、足がふらついて転んでしまった。
鶴町は、そんな様子を見て
「仕方のない奴だな。」
と、僕に手を差し出した。鶴町の手は暖かかった。
屋上は、一面夕焼けだった。街も樹も山も畑もみんな真っ赤に染まっていた。僕は鶴町と給水塔の下の段差に腰かけた。
「さっき話しだけど・・・。」
切り出したのは鶴町だった。
「お前が話してくれたから、俺も言うけど今から話すことは絶対秘密にしていてくれ、今そう誓え!!」
不仕付で横暴な鶴町に圧倒された僕は
「わかった。誓う・・・。」
と、返事した。
僕はこれから鶴町の意外な過去を聞く。
「俺、ちょっとだけ少年院に入ってたことがある・・・。」
「俺の母さんは俺を産むと他界した。俺は父親に育てられた。片親というのははっきり言ってつらいもんだよ。小さい頃から親父は仕事、仕事で俺には構ってくれない。
夜一人で眠る淋しさをまぎらわせる為に俺は夜になると街に出回るようになった。ネオンの下には人間がいた。活気があった。俺が気がついた頃には、この明かりの下に群がる連中たちと一緒にバカをやっていた。金がなくなったら平気で街の親父どもを叩きのめし金を取った。その金でいいモノを食って商売女も抱いた。気にいらない奴は半殺しにした。
その頃の俺は、まるで何かに憑かれたように街へくり出しては暴れた。でも金があっても気にいらない奴の腕をへし折っても、俺は満たされることはなかったんだ・・・。
〝これを打つと極楽へ行けるよ〟そんな薬の売人のあおり文句が俺を夢中にさせた。俺は親父狩りでためこんだ金を全部ヘロインにつぎこんでいった。白い粉を溶かし込んだ注射器何度も腕に刺した。極楽というのか頭の芯が痺れて、うっとりした。現実からの解放。このままそれが永遠になって欲しいと願った。そうだ。俺は何かから逃げ出したかったのかもしれない。俺はいつしか覚醒剤なしでは生きていけない体になっていたんだ。
親父に見つかったのは路上で倒れている俺を警察が呼んだからだ。俺は親父狩りできる体力もなかった。うつろな瞳で親父を見上げたら、親父は俺をおもいっきりぶん殴りやがった。警察が薬物中毒看者用の病院を手配したが親父は、家に連れて帰るといいはってそれから親父と俺の戦争が始まった。薬が切れると、人が化け物に見える。親父も例外じゃなかった。暴れる俺に親父が近づいてくる。それだけで俺には十分すぎる程の地獄だった。笑う声、罵しる声、獣の声、車の音、歪んだ空間ここがどういう世界なのかわからなかった。絨毯を這う、体のちぎれた男、水道の蛇口から出る海月、こっちに向かってくる暴炎、見えない恐怖に怯え、自分の出す叫びはもはや人間の声ではなかった。エリートだった親父は会社をやめ、俺につきっきりになった。力強く俺を押さえつけ何時間も同じ体制で俺についていた。「大丈夫だ。お前は強い子だ。だから大丈夫だ。」俺にいっているのか、自分でいいきかせているのかわからなかった。
「それは薬がぬける少し前だった。俺はどうしょうもない恐怖心から逃げたくて親父の財布をくすねて薬の売人の所へ行こうとした。親父は止めに俺の背中から腹にかけて腕をまわした。俺は、その腕をふり切ると台所にある包丁で親父めがけて飛び込んだ。
――親父はよけなかった・・・。
右腹を押さえて、
『つらかったな・・・。』
とだけ言って倒れたんだ。」
鶴町は夕日を見ながら淡々と語る。でも肩が震えていた。
「お前に俺の宝物を見せてやるよ。」
そういって僕に手渡されたのは黄色くなった皺皴の封筒だった。表には
〝明へ〟
と書いてある。
鶴町の父が鶴町に宛てた手紙だった。
〝明。元気でやっているか。少年院の生活には慣れたか?父さんの方は今、新しい建築物の設計で忙しい。お前に会えにいけないので手紙を書くことにした。
明、お前は、母さんが命をかけて産んだ私の形見だ。『明』という名は母さんが名付けたものだ。明けの明星に産声をあげたお前を母さんは、『明るく輝いて生きる子に育つように』という意味ををこめた。母さんは、
「私の宝物、あなたにあげる。大切にして。」
と言って死んでいった。お前を大切にしたかったのに、少年院(そんなところ)にやった自分を情けなく思う。だがな、明。どんな所にいても、お前はお前らしく輝いて生きて行け!決して死ぬな!生きていてさえくれればいい。どんなに社会に打ちのめされても、父さんはいつだって見方だ。だってお前はこの世でたった一人の父さんと母さんの自慢の息子なんだから。私の一人は淋しいんだ。明、早く帰ってこい〟
手紙を読み終ると鶴町は続けた。
「それを少年院で読んで嬉しかったんだよ。俺それまで親父から母さんを奪ったのは自分だって思ってた。俺は、こんなにも愛されて望まれて生まれてきたんだって。ホント誇りに思うよ。そしてね・・・。気付いたんだ。俺が半殺しにした奴の親も親父のように泣いてたんじゃないかって・・・。」
死んでもいい親なんていない。
望まれない子供なんていない。
僕たちはそう確かめ合った。
二人で黙って夕焼けを見る。本当にきれいな空だった。茜雲がゆっくりと通りすぎ、新しい雲を呼ぶ。その雲の輪郭を夕日が映し出した。僕達は同じモノを見ていた。
鶴町にはかなわない。これじゃあ南も好きになるわけだ。そう思って
「なぁ、鶴町、南を大切にしてやれよ・・・。」
と言うと、鶴町はキョトンとした顔をした。
「何言ってんの?お前、南はお前にゾッコンだぜ。何を勘違いしているのかは知らないが、お前が元気がないって、ずっと悩んでいたぜ。全くそう言うことは本人に話せっつうの!相談される身にもなってみろよ・・・。アレ・・・?もしかしてお前、妬いてたのか?」
鶴町は意地悪そうにニヤニヤ笑った。僕は恥ずかしくなってうつむいて、黙ってしまった。
完
--------------------------------------------------------------------------------
散文(批評随筆小説等) ロクデナシ Copyright 為平 澪 2009-03-03 04:06:21縦
-
最近の投稿
カテゴリー
最近のコメント
カウンター
77,216アーカイブ
- 2024年1月 (2)
- 2022年6月 (1)
- 2022年4月 (3)
- 2021年5月 (2)
- 2021年3月 (1)
- 2021年2月 (2)
- 2020年12月 (2)
- 2020年9月 (1)
- 2020年8月 (1)
- 2020年7月 (1)
- 2020年6月 (1)
- 2020年4月 (1)
- 2020年3月 (6)
- 2019年12月 (4)
- 2019年6月 (2)
- 2019年3月 (2)
- 2019年2月 (4)
- 2018年12月 (3)
- 2018年9月 (2)
- 2018年8月 (2)
- 2018年7月 (5)
- 2018年6月 (1)
- 2018年5月 (1)
- 2018年4月 (1)
- 2018年3月 (1)
- 2018年2月 (2)
- 2018年1月 (4)
- 2017年12月 (4)
- 2017年11月 (1)
- 2017年10月 (1)
- 2017年9月 (2)
- 2017年8月 (4)
- 2017年6月 (4)
- 2017年5月 (2)
- 2017年3月 (2)
- 2017年2月 (3)
- 2017年1月 (1)
- 2016年12月 (3)
- 2016年11月 (4)
- 2016年10月 (2)
- 2016年9月 (5)
- 2016年7月 (4)
- 2016年6月 (4)
- 2016年5月 (1)
- 2016年4月 (1)
- 2016年3月 (4)
- 2016年2月 (4)
- 2016年1月 (3)
- 2015年12月 (1)
- 2015年11月 (4)
- 2015年10月 (6)
- 2015年9月 (4)
- 2015年8月 (3)
- 2015年7月 (5)
- 2015年6月 (4)
- 2015年5月 (5)
- 2015年4月 (8)
- 2015年3月 (7)
- 2015年2月 (3)
- 2015年1月 (4)
- 2014年12月 (4)
- 2014年11月 (7)
- 2014年10月 (5)
- 2014年9月 (10)
- 2014年8月 (14)
- 2014年6月 (1)
- 2014年5月 (6)
- 2014年4月 (6)
- 2014年3月 (11)
- 2014年2月 (6)
- 2014年1月 (3)
- 2013年12月 (2)
- 2013年10月 (5)
- 2013年9月 (6)
- 2013年8月 (4)
- 2013年7月 (9)
- 2013年6月 (7)
- 2013年5月 (5)
- 2013年4月 (3)
- 2013年3月 (3)
- 2013年2月 (9)
- 2013年1月 (3)
- 2012年12月 (6)
- 2012年11月 (6)
- 2012年10月 (9)
- 2012年9月 (8)
- 2012年8月 (12)
- 2012年7月 (10)
- 2012年6月 (6)
- 2012年5月 (8)
- 2012年4月 (8)
- 2012年3月 (6)
- 2012年2月 (6)
- 2012年1月 (12)
- 2011年12月 (7)
- 2011年11月 (9)
- 2011年10月 (6)
- 2011年9月 (9)
- 2011年8月 (10)
- 2011年7月 (15)
- 2011年6月 (5)
- 2011年5月 (14)
- 2011年4月 (13)
- 2011年3月 (15)
- 2011年2月 (11)
- 2011年1月 (10)
- 2010年12月 (9)
- 2010年11月 (8)
- 2010年10月 (14)
- 2010年9月 (18)
- 2010年8月 (20)
- 2010年6月 (10)
- 2010年5月 (14)
- 2010年4月 (12)
- 2010年3月 (17)
- 2010年2月 (13)
- 2010年1月 (14)
- 2009年12月 (4)
- 2009年11月 (8)
- 2009年10月 (19)
- 2009年9月 (29)
- 2009年8月 (5)
- 2009年7月 (1)
- 1970年1月 (1)