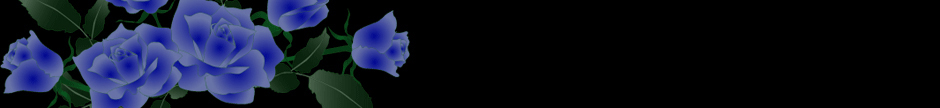父は、事業が行き詰まり大阪へ単身赴任を余儀なくされた。平成九年深夜、胸に激痛を感じた父は、携帯から救急車を呼び診断の結果、胆石の手術のため済生会病院に入院。しかし、短時間で終わるはずの手術が長時間に及び、執刀医のミスで一晩中出血が止まらなかった。翌日再手術。「輸血された血液製剤はミドリ十字社のものだ」と、告知されたのは、父がC型肝炎を発病して数年後のことである。母と弟が主治医のパソコンに向き合いながら、説明を受けた。
C型肝炎訴訟には追い付けない。平成六年までの患者が対象。しかし、全ての非加熱製剤はなくなった、となぜ保証できるのだろう。在庫処分の犠牲になった人々が本当にいないかは私には甚だ疑問である。そんな思惑が頭を掠る内、父のC型肝炎は日を追うごとに悪化。平成十八年八月、検査入院して打ち続けたインターフェロンに体は適応できず断念。慢性肝炎と診断される頃には、父はとうとう兵庫の実家に帰省。大阪では使いものにならないと言われた体を引きずりながら、それでも家族を養えるのは自分だけだと、老人介護施設の門番の仕事を選び、市役所に申請してまでも働き続けた。
しかし、病状は急変。平成二十六年には、検査入院と自宅介護が繰り返された。深夜に、一つのフロアーを、三人の看護士で十三人の利用者を見回る田舎の総合病院。徘徊する者の服の裾をベッドの端に括り付け、動ける足でトイレに行けた患者すら足が弱り、おむつ介護の身になった。命は簡単に変動し、奪われて出ていく者と、息をしているだけの者。あるいは、その時を待つ者しか、残らなかった。それは老人介護施設で長期間働いていた父には予想できた光景だったに違いない。
平成二十六年四月。その施術は執行。「腹腔穿刺」は家族の誰にも説明はなく、「どいてください」と、寄り添っていた母を追い出し、父のベッドは全てカーテンで隠された。出てきた父の腰の下あたりには手術後の包布の切れ端が落ちていた。「なぜ、家族に十分な説明もなく手術したのですか?」と、のちに問うと、担当医は「緊急事態でしたので本人に了解を取りました」と言い放った。しかし既に六か月前「肝臓の悪化による意識障害」が、父のカルテには記載されていた。
最期の日、個室に移動させられた父のベッドのすぐ下に「ビタメジン静注用」というショッキングピンクの水溶液が残る小瓶を発見。カルテの開示の時、私はあの小瓶が気になって目の前の事務員の男性に「ビタメジン静注用を投薬したのはいつですか?」と聞くと、男性はすぐに主治医に内線で連絡をとり、「四月十四日です」と答えた。それは父が亡くなった日。カルテの記録に「ビタメジン静注用」使用の記載は一切されていない。
父の葬儀三日後、「病院を変えて肝炎の菌が全て消えた」と、父と同時に闘病をしていたおじさんが訪れてきた。私は何も言いたくなかった。ただ俯いて、「父は三日前に亡くなりました。」としか、言えなかった。
その二週間後、神戸国際メディカルセンターで「肝臓移植で七人が死亡」というニュースが報道される。そして今年、同センターで、「犠牲者が十一人に上った」と耳にした。
※
「いのちのことを、言うていかなあかんなぁ」
口がきけなくなる前の父の最後の言葉が、今、重く圧し掛かる。
※女性詩誌 something24 掲載原稿
-
最近の投稿
カテゴリー
最近のコメント
カウンター
77,216アーカイブ
- 2024年1月 (2)
- 2022年6月 (1)
- 2022年4月 (3)
- 2021年5月 (2)
- 2021年3月 (1)
- 2021年2月 (2)
- 2020年12月 (2)
- 2020年9月 (1)
- 2020年8月 (1)
- 2020年7月 (1)
- 2020年6月 (1)
- 2020年4月 (1)
- 2020年3月 (6)
- 2019年12月 (4)
- 2019年6月 (2)
- 2019年3月 (2)
- 2019年2月 (4)
- 2018年12月 (3)
- 2018年9月 (2)
- 2018年8月 (2)
- 2018年7月 (5)
- 2018年6月 (1)
- 2018年5月 (1)
- 2018年4月 (1)
- 2018年3月 (1)
- 2018年2月 (2)
- 2018年1月 (4)
- 2017年12月 (4)
- 2017年11月 (1)
- 2017年10月 (1)
- 2017年9月 (2)
- 2017年8月 (4)
- 2017年6月 (4)
- 2017年5月 (2)
- 2017年3月 (2)
- 2017年2月 (3)
- 2017年1月 (1)
- 2016年12月 (3)
- 2016年11月 (4)
- 2016年10月 (2)
- 2016年9月 (5)
- 2016年7月 (4)
- 2016年6月 (4)
- 2016年5月 (1)
- 2016年4月 (1)
- 2016年3月 (4)
- 2016年2月 (4)
- 2016年1月 (3)
- 2015年12月 (1)
- 2015年11月 (4)
- 2015年10月 (6)
- 2015年9月 (4)
- 2015年8月 (3)
- 2015年7月 (5)
- 2015年6月 (4)
- 2015年5月 (5)
- 2015年4月 (8)
- 2015年3月 (7)
- 2015年2月 (3)
- 2015年1月 (4)
- 2014年12月 (4)
- 2014年11月 (7)
- 2014年10月 (5)
- 2014年9月 (10)
- 2014年8月 (14)
- 2014年6月 (1)
- 2014年5月 (6)
- 2014年4月 (6)
- 2014年3月 (11)
- 2014年2月 (6)
- 2014年1月 (3)
- 2013年12月 (2)
- 2013年10月 (5)
- 2013年9月 (6)
- 2013年8月 (4)
- 2013年7月 (9)
- 2013年6月 (7)
- 2013年5月 (5)
- 2013年4月 (3)
- 2013年3月 (3)
- 2013年2月 (9)
- 2013年1月 (3)
- 2012年12月 (6)
- 2012年11月 (6)
- 2012年10月 (9)
- 2012年9月 (8)
- 2012年8月 (12)
- 2012年7月 (10)
- 2012年6月 (6)
- 2012年5月 (8)
- 2012年4月 (8)
- 2012年3月 (6)
- 2012年2月 (6)
- 2012年1月 (12)
- 2011年12月 (7)
- 2011年11月 (9)
- 2011年10月 (6)
- 2011年9月 (9)
- 2011年8月 (10)
- 2011年7月 (15)
- 2011年6月 (5)
- 2011年5月 (14)
- 2011年4月 (13)
- 2011年3月 (15)
- 2011年2月 (11)
- 2011年1月 (10)
- 2010年12月 (9)
- 2010年11月 (8)
- 2010年10月 (14)
- 2010年9月 (18)
- 2010年8月 (20)
- 2010年6月 (10)
- 2010年5月 (14)
- 2010年4月 (12)
- 2010年3月 (17)
- 2010年2月 (13)
- 2010年1月 (14)
- 2009年12月 (4)
- 2009年11月 (8)
- 2009年10月 (19)
- 2009年9月 (29)
- 2009年8月 (5)
- 2009年7月 (1)
- 1970年1月 (1)