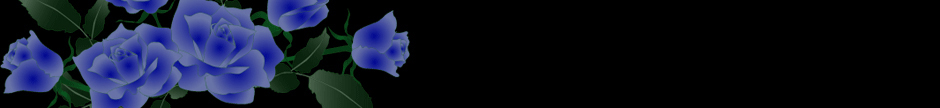こんなネオンの華やぐ街で あなたは暮らしているのでしょうか
高速道路からでも立ち並ぶ マッチ箱の灯りの何処かに
あなたの名前を 探しています
あの日泣きながら バーテンダーが繰り出すマッカランを
浴びるほど飲んでみたいと 潤んでいたあなたは
私の涙腺の端しっこに 住んでいます
バス停から乗車してくる群衆に 乗らなかった人
それがあなたであったと 知る頃には
次の停留所に向かう放送に 面影は追い越され
距離だけが 植え込みの並木を見送って 長い影を走らせます
よく変わるチェーン店のように あなたがまた遠くへ
引っ越しては明るい暮らしに 馴染んでいると知りました
(プロポーズされました、春、桜だったものが、秋桜と呼ばれています。)
ポストに一枚 そんな病葉のような 葉書でも欲しかったのです
私はただ あなたが乗り遅れたと言い訳してくれたら
マッカランを 浴びるほど飲ませたくて
酔った勢いで やり直そうと
もう決して言えない言葉に 焦がれながら
あの日浚われた言葉が 乗り遅れたどこかのバスの停車駅に
まだ 灯ってはいないかと 家路にたどり着くまで 探しています
マッカランの色に酔っていたのは 私の方だと噛み締めながら
二人座ったカウンターは 廃業したのですね
多分 もう一杯飲めると笑ったあなたも
それに怯えたマスターの顔も 私の乗ってるバスは知らない顔で
いりくんだ暗い【し】というトンネルを 抜けきれず
私達は 急ブレーキをよけきれないまま 飲酒運転で 死にました
あなたは桜に戻って 私はあなたを照す月に変わって・・・
-
最近の投稿
カテゴリー
最近のコメント
カウンター
77,166アーカイブ
- 2024年1月 (2)
- 2022年6月 (1)
- 2022年4月 (3)
- 2021年5月 (2)
- 2021年3月 (1)
- 2021年2月 (2)
- 2020年12月 (2)
- 2020年9月 (1)
- 2020年8月 (1)
- 2020年7月 (1)
- 2020年6月 (1)
- 2020年4月 (1)
- 2020年3月 (6)
- 2019年12月 (4)
- 2019年6月 (2)
- 2019年3月 (2)
- 2019年2月 (4)
- 2018年12月 (3)
- 2018年9月 (2)
- 2018年8月 (2)
- 2018年7月 (5)
- 2018年6月 (1)
- 2018年5月 (1)
- 2018年4月 (1)
- 2018年3月 (1)
- 2018年2月 (2)
- 2018年1月 (4)
- 2017年12月 (4)
- 2017年11月 (1)
- 2017年10月 (1)
- 2017年9月 (2)
- 2017年8月 (4)
- 2017年6月 (4)
- 2017年5月 (2)
- 2017年3月 (2)
- 2017年2月 (3)
- 2017年1月 (1)
- 2016年12月 (3)
- 2016年11月 (4)
- 2016年10月 (2)
- 2016年9月 (5)
- 2016年7月 (4)
- 2016年6月 (4)
- 2016年5月 (1)
- 2016年4月 (1)
- 2016年3月 (4)
- 2016年2月 (4)
- 2016年1月 (3)
- 2015年12月 (1)
- 2015年11月 (4)
- 2015年10月 (6)
- 2015年9月 (4)
- 2015年8月 (3)
- 2015年7月 (5)
- 2015年6月 (4)
- 2015年5月 (5)
- 2015年4月 (8)
- 2015年3月 (7)
- 2015年2月 (3)
- 2015年1月 (4)
- 2014年12月 (4)
- 2014年11月 (7)
- 2014年10月 (5)
- 2014年9月 (10)
- 2014年8月 (14)
- 2014年6月 (1)
- 2014年5月 (6)
- 2014年4月 (6)
- 2014年3月 (11)
- 2014年2月 (6)
- 2014年1月 (3)
- 2013年12月 (2)
- 2013年10月 (5)
- 2013年9月 (6)
- 2013年8月 (4)
- 2013年7月 (9)
- 2013年6月 (7)
- 2013年5月 (5)
- 2013年4月 (3)
- 2013年3月 (3)
- 2013年2月 (9)
- 2013年1月 (3)
- 2012年12月 (6)
- 2012年11月 (6)
- 2012年10月 (9)
- 2012年9月 (8)
- 2012年8月 (12)
- 2012年7月 (10)
- 2012年6月 (6)
- 2012年5月 (8)
- 2012年4月 (8)
- 2012年3月 (6)
- 2012年2月 (6)
- 2012年1月 (12)
- 2011年12月 (7)
- 2011年11月 (9)
- 2011年10月 (6)
- 2011年9月 (9)
- 2011年8月 (10)
- 2011年7月 (15)
- 2011年6月 (5)
- 2011年5月 (14)
- 2011年4月 (13)
- 2011年3月 (15)
- 2011年2月 (11)
- 2011年1月 (10)
- 2010年12月 (9)
- 2010年11月 (8)
- 2010年10月 (14)
- 2010年9月 (18)
- 2010年8月 (20)
- 2010年6月 (10)
- 2010年5月 (14)
- 2010年4月 (12)
- 2010年3月 (17)
- 2010年2月 (13)
- 2010年1月 (14)
- 2009年12月 (4)
- 2009年11月 (8)
- 2009年10月 (19)
- 2009年9月 (29)
- 2009年8月 (5)
- 2009年7月 (1)
- 1970年1月 (1)