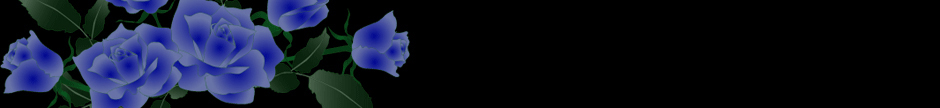憧れる街は いつもディスプレイの中
モニターに入って人混みに紛れてみると
誰かの指で私はデジタル文字にされたり 欠けた映像として
スクロールされておぼれて消える
明日の浮遊物が明後日の沈殿物になる街の
七十五日の話題を追いかけても
答えは前後左右に散らばるだけの罠
現世を映す鏡を人差し指で弾く人の、揚げ足をとり
また人差し指が、はじく、はじく、また誰かを指す、その指
会話をなんとか縫合しようとしてみたら
今度は親指で話題を葬るバーチャルリアリティー
小さな古家に住んでいた祖母が言っていた言葉
(阿弥陀さんが、みんな見とるから安心してここで暮らしたらええ
その「ここ」からとても遠い場所でぼんやり光る夜光虫は
おばあちゃんの鍬も鋤もどこにしまったか忘れてしまったし
さつまいもの植え方を教えてくれた父はもういない
私の鎌も錆び付き草刈りの仕方も忘れて畑は荒れ放題
ディスプレイから私を覗けば私は人の住めなくなった廃屋を
大切そうに見せびらかしながら歩いてた
街では成り上り者が虚勢の名を荒らげていく
そういうことを 一番嫌がっていたはずなのに
自分が成り上り者だと指を指される頃に気づく
街の見晴らしは とても高く、そして足元は脆かった
足下のマンホールから人の死臭を帯びた風がいつも噴き上げて
その臭いが 身に染みていくのが怖かった
ネオンは青から黄色、そして赤へと 空高く昇っていく
街は こんなに華やかなのに
人は こんなに賑やかなのに
今、この瞬間に「誰か友達いますか」と
問われると 黙って俯くことしかできない
私はどこにいるんだろう
どこに行けばいいんだろう
これからどうすればいいんだろう
空騒ぎして明日になると宛も無くなる人と
容易く乾杯して作り笑いを見せて別れてしまえば
私の手と手が真っ直ぐ私の首を絞めにきた
夕陽の沈まない街の、
夕日が沈んだり浮いたりして川に毎日捨てられる泥水の、
その、夕陽が残していくものだけは覚えていて胸は高鳴った
私の古臭い町にも同じ太陽が沈んでいる、と
思い出したら 赤い色が滲んで落ちた
帰りたいのか、出て行きたいのか
戻りたいのか、忘れたいのか
空いっぱい黄金色に広がる手のひらの、大きさ、厚さ、懐かしさ
はじめから孫悟空
私の手で掴めたものなど何もないと知ったとき
逃げても逃げても追いかけて正面から向き合ってくれた人と
真っ正直に沈むあの夕陽の町
みんながみんな居なくなった あばら家の
テーブルの上に置き去りにされた阿弥陀如来
今もそこで 私の何処を見てますか
※同人誌「NUE」寄稿原稿⑤
-
最近の投稿
カテゴリー
最近のコメント
カウンター
79,812アーカイブ
- 2025年4月 (2)
- 2024年1月 (2)
- 2022年6月 (1)
- 2022年4月 (3)
- 2021年5月 (2)
- 2021年3月 (1)
- 2021年2月 (2)
- 2020年12月 (2)
- 2020年9月 (1)
- 2020年8月 (1)
- 2020年7月 (1)
- 2020年6月 (1)
- 2020年4月 (1)
- 2020年3月 (6)
- 2019年12月 (4)
- 2019年6月 (2)
- 2019年3月 (2)
- 2019年2月 (4)
- 2018年12月 (3)
- 2018年9月 (2)
- 2018年8月 (2)
- 2018年7月 (5)
- 2018年6月 (1)
- 2018年5月 (1)
- 2018年4月 (1)
- 2018年3月 (1)
- 2018年2月 (2)
- 2018年1月 (4)
- 2017年12月 (4)
- 2017年11月 (1)
- 2017年10月 (1)
- 2017年9月 (2)
- 2017年8月 (4)
- 2017年6月 (4)
- 2017年5月 (2)
- 2017年3月 (2)
- 2017年2月 (3)
- 2017年1月 (1)
- 2016年12月 (3)
- 2016年11月 (4)
- 2016年10月 (2)
- 2016年9月 (5)
- 2016年7月 (4)
- 2016年6月 (4)
- 2016年5月 (1)
- 2016年4月 (1)
- 2016年3月 (4)
- 2016年2月 (4)
- 2016年1月 (3)
- 2015年12月 (1)
- 2015年11月 (4)
- 2015年10月 (6)
- 2015年9月 (4)
- 2015年8月 (3)
- 2015年7月 (5)
- 2015年6月 (4)
- 2015年5月 (5)
- 2015年4月 (8)
- 2015年3月 (7)
- 2015年2月 (3)
- 2015年1月 (4)
- 2014年12月 (4)
- 2014年11月 (7)
- 2014年10月 (5)
- 2014年9月 (10)
- 2014年8月 (14)
- 2014年6月 (1)
- 2014年5月 (6)
- 2014年4月 (6)
- 2014年3月 (11)
- 2014年2月 (6)
- 2014年1月 (3)
- 2013年12月 (2)
- 2013年10月 (5)
- 2013年9月 (6)
- 2013年8月 (4)
- 2013年7月 (9)
- 2013年6月 (7)
- 2013年5月 (5)
- 2013年4月 (3)
- 2013年3月 (3)
- 2013年2月 (9)
- 2013年1月 (3)
- 2012年12月 (6)
- 2012年11月 (6)
- 2012年10月 (9)
- 2012年9月 (8)
- 2012年8月 (12)
- 2012年7月 (10)
- 2012年6月 (6)
- 2012年5月 (8)
- 2012年4月 (8)
- 2012年3月 (6)
- 2012年2月 (6)
- 2012年1月 (12)
- 2011年12月 (7)
- 2011年11月 (9)
- 2011年10月 (6)
- 2011年9月 (9)
- 2011年8月 (10)
- 2011年7月 (15)
- 2011年6月 (5)
- 2011年5月 (14)
- 2011年4月 (13)
- 2011年3月 (15)
- 2011年2月 (11)
- 2011年1月 (10)
- 2010年12月 (9)
- 2010年11月 (8)
- 2010年10月 (14)
- 2010年9月 (18)
- 2010年8月 (20)
- 2010年6月 (10)
- 2010年5月 (14)
- 2010年4月 (12)
- 2010年3月 (17)
- 2010年2月 (13)
- 2010年1月 (14)
- 2009年12月 (4)
- 2009年11月 (8)
- 2009年10月 (19)
- 2009年9月 (29)
- 2009年8月 (5)
- 2009年7月 (1)
- 1970年1月 (1)